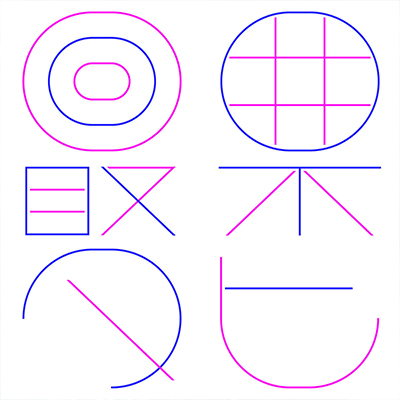
最果タヒ
詩人
1986年生まれ。詩人。詩やエッセイ、小説など、幅広く執筆活動を行なっており、中原中也賞や現代詩花椿賞など、数々の賞を受賞。
最果タヒの詩集がブックオフに置いてある! とネットで言われていることがたまにあって、そういうのを聞くたびに自分が本を売った時のことを思い出す。大抵そういうことを言われるのは、古本に詩集があるのってなんか……迫力があるね……みたいな意味合いなので多分そんないい印象ではないのだろうなと思うのだけど。せっかくだし、自分がそのことについてどう思うか書いてみたい。
詩集を買ってくれた人が、ずっと自分の本棚に置いてくれて、50年後もその本棚の住人として詩集がいたらそんな奇跡みたいなことはないと思う。私は人と50年後も友達でいる自信が全くないし、自分の周囲にいる人が「友達」なのかもわからないことが多いけれど、でも、それでも本がこの星のどこかで一人ぐらいには一生の友として扱われる日があるのかもしれないと思うと、それはとてつもないことだ。二億冊売れる本を書けるとは思ってないけど、誰かの本棚に50年残る本が書けたらいいなとは心底思う。そして同時に、それを全ての読者に祈っているわけではないなとも思っている。
「二億冊売れるような本は多分出せないが、誰かの本棚に50年残る本が出せたらいいな。長く開かなくてもいいよ、本棚にいることも本の仕事だから。」
ツイッターに先日これを書いたときに考えていた。確かにそれは私の願いだけど、私の作品を好きな人に「だからずっと置いていてください」と言いたいわけではないと。偶然にもその人の選択としてそうなればいいけど、そうしてくれることだけが私の幸福かというとそんなわけはない。
飽きてOKって昔、ブログに書いたことがあった。私のファンの人が、あのころみたいな詩を書いてください、って昔の作品を指して言うこともあった。とてもありがたいことだけど、「あの頃みたいな詩」はもうすでにあって、今作る意味はないと私はどうしても思ってしまう。美学とかではなくて単純に書くときに新鮮な気持ちになりたいから、私は自分の楽しさを優先してそう思ってしまう。そういうのがわかっているから、私の作品を好きだと言う人に「すべてを好きになって」とも「ずっと好きでいて」とも言えず、「好きでなくなったとしても仕方ないよ」と言いたくなる。それはもしかしたら好きと言ってくれる人たちに対して淡白すぎるのかもしれないが、でもやっぱり私は読者と人としてずっと付き合いがある存在になりたいのではなく、本棚にささっている「一冊」でありたいのだ。そのささやかさが好きで、もちろん、新しく書いたものを「もう誰も好きじゃないかもな」と不安に思うことはあるけど、その新しい一冊を、私の読者かまだ読者でない人の誰か一人が本棚に置きたいと思ってくれるようにがんばるしかない。ずっと何を書いても最果の作品ならと好きでいてくれることと、読み手が「ぼくの一冊」「私の一冊」として一つの作品を本棚に置いて、私の全著作を知っているわけではないけど、その一冊がその人の人生の一部になること、どちらの方が尊いとか、あるだろうか。きっとない。私は人なので、もちろん飽きられるかもなぁとか、読まれなくなるかなぁとか考えるし不安もあるけど、その気持ちから救ってくれる存在が読者な訳ではなく、読者はずっと「作者」という人の感情から、解き放たれていてほしい、自由でいてほしい。作品だけを愛せる環境でいてほしい。
そして、もちろんその人が特別に愛した作品が、わからなくなったりする日もくるのかもしれないと、知っている。
私だってずっと変わるし、それは読み手だって同じで、ずっと同じ作品を好きでいられることってきっとそうそうない。本棚にずっと置くのももしかしたらずっと好きだというのとはまた違うのかもしれない。詩集だと、読むたびに好きだと思う作品が違う、と言われることもあるし、その毎回の違いが面白くて本棚に置いているという人もいるのかもしれない。そして一方でどうしても本棚に置くのが許せなくなることもあるだろう。でも、そんな大事な人生の変わり目に私が書いた本があるなんて、なんて幸福なことだろうと思う。私個人としては、そうなんだ……とすこしさみしくもあるけど、そんな大事な瞬間にリトマス紙のようにある自分の作品のこと、他人事みたいに尊敬してしまう。私は人間として誰かにとってそんな重要な存在になれたことあるだろうか。きっとないな。さみしいけどそれはこちらの問題で、とんでもないところまで作品を連れて行ってくれたその読者に感謝したくなってしまう。
詩は、書き手としての私の気持ちを吐露した作品というよりは、読み手の「私の気持ち」になっていくものだと思う。ふとした時「これは自分の言葉だ」と読む人が感じた瞬間、言葉はその人に急激に接近し、手放せない言葉として残るのかもしれません。決してそれは絶対的な「答え」としてあるのではなくて、読んだ人の感想を聞くと、書いていた時に私が想定したものをそのまま読み取っている人ってほとんどいなくて、むしろ、その人に溶け込むように形を変えている。読者がその詩を完成させているんだと思います。そしてそうした変化を許す曖昧さが「近づいていく力」になるのだと思っています。
自分がどんな人間かなんて、誰にもわからないことなのだ。それをはっきりさせる言葉に振り回されたりもするけど、でも人間はそもそもそんなに白黒はっきりしているわけではない。「わからないこと」こそが一番のその人の「本当」で、無理に白黒をつけようとするたびに四捨五入するものが出てしまう気がしている。詩は、言葉で白黒をつけるのではなく、その曖昧さを曖昧さのままで書くものなのだと思っている。だからこそ、読者の「自分だけの言葉」に詩はなっていけるのかなって。わからなさをそのままにして近づいていける言葉なのかもしれません。
お互いの性格を完全に理解しているわけではないけど、それでも友達でいるようなことかもしれない。一生絶対に友達だと誓い合うより、もしかしたらそれは尊いことなのかもしれず、だから、詩が永遠にその人にとって大切な作品であってほしいとは、私は思わない。ある瞬間にとても大切で、また違うタイミングでは全くわからなくなることもあるだろう。それが軽いことだとは言えない、むしろその人と共に生きたってことだと思っている。
古本屋に自分の詩集があると、昔は私の書いた言葉と友達だった誰かがそこにいた気がして不思議な感覚になる。読者に自分の詩について好きなものもあればよくわからないものもあると言われることも気にならない。好きだったのに急にわからなくなったという話も、言われることはあるけれどそれは当たり前だから、そうだったんですね、と答えている。そうやって私の見えないところで私の言葉と出会って別れてる人がいるんだなあ、私にはできないことを私の言葉はたくさんしていて、すごいなぁって、古本屋で思う日もあった。(もちろんそりゃ、買って最初からよくわかんなくて手放したってパターンもあるだろう、それはもうほんまごめんねの気持ちです。)人間は友達がいま何人いるとかそういう話はするけれど、「友達だったけど縁が切れてしまった人」の数をよく知らない、考えようともしなくて、でもそれはものすごく大切なことである気がする。人生のある一瞬を決定づけるワンシーンにいた一冊になれるなら、私は嬉しい。古本屋で、私の言葉を昔好きだった人がいた、ということをそこに感じるのは、決して悪いことではないはずだ。
などと、言いながら、書店で自分の詩集を立ち読みしている高校生が、何篇か読んだあと、ちらと後ろの本の値段を見たとき、私はとてもどきどきしていた。好きになってもらえるならもちろん嬉しい。私は私じゃなくなることができないので、いつまでも私の気持ちとともにあるので、読んでくれるなら嬉しいし、50年後、本棚にずっと置いていますって詩集を見せられたら嬉しい、それは本当に変わらない。ただ、それが全てではないしそれだけを幸せだと思うのは、もったいないって思っているだけだ。別れで終わった幸福について語るのはとても難しく、誤解も生まれやすいけれど、それでも幸福なことだと改めて、別れを経験した本を前にしてちゃんと言ってみたくなった。高校生のあの子が、私の詩集を買ってくれたとしてその先にあるのが50年でも1ヶ月でも、私はやっぱりとても奇跡的なことだと思う。
TEXT:最果タヒ
PHOTO:ブックオフをたちよみ!編集部
【ブックオフへの思いが綴られたエッセイ】
【大きなブックオフに行けば、読みたいエッセイ本も見つかるかも?】
この記事はおもしろかった?

